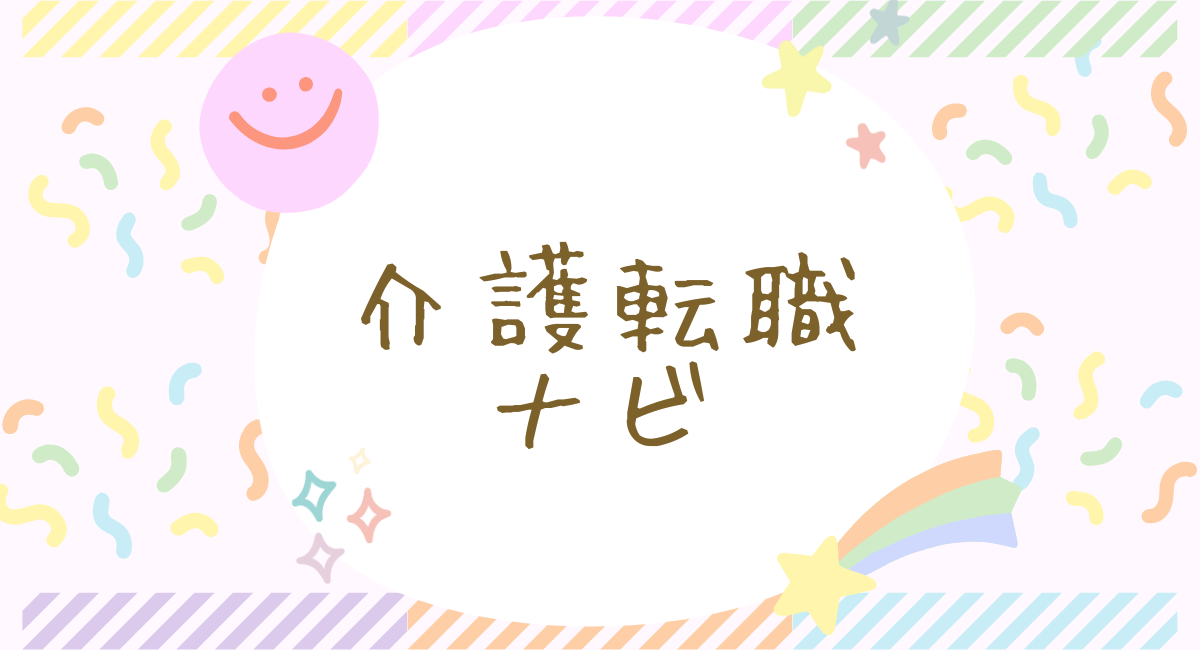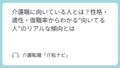私が介護施設で働き始めてから、もう十数年が経ちます。最初の頃、スタッフはほとんどが日本人で、施設内で外国語を耳にすることはほとんどありませんでした。けれど、この数年で状況は大きく変わりました。今では、施設のスタッフの1~3割を外国人が占めるようになり、日常の風景の中に自然と多国籍な空気が混ざっています。
厚生労働省のデータによれば、2024年12月時点で「特定技能」で働く介護分野の外国人は約44,000人。技能実習やEPA介護福祉士候補者を合わせると、医療・福祉分野全体で85,000人を超えているそうです。数字を目にしたとき、私自身も「そうか、やっぱり肌で感じていた変化は間違っていなかったんだ」と思いました。
最初の戸惑い
正直に言うと、最初は戸惑いの連続でした。例えば、利用者さんが食事の前後に必ず「いただきます」「ごちそうさま」と口にするのは、日本人にとって当たり前のこと。でも、外国人スタッフの中にはその習慣を知らず、挨拶を省いてしまうことがありました。そのときに利用者さんから「この人は挨拶をしない」と不満が出て、間に立つ私もどう伝えるべきか悩んだことがあります。
また、日本人特有の「遠慮」の感覚も大きな壁でした。利用者さんが「大丈夫」と言いながら実は困っている、ということはよくあります。しかし、外国人スタッフはその言葉をそのまま受け取ってしまい、本当に支援が必要な場面を見逃してしまうのです。
当時は「文化の違い」をどう埋めればいいのか分からず、時には小さな衝突が起こることもありました。
一緒に学び合う時間
そんな中、施設では外国人スタッフ向けの研修や勉強会を設けるようになりました。単に介助方法を教えるだけではなく、「日本の介護文化」や「利用者との接し方」についても共有する時間です。
ある時、ベトナム出身のスタッフが「日本語で『大丈夫』と言われた時、本当に大丈夫かどうか分からない」と質問してくれました。その場で私たち日本人スタッフが実例を交えて説明し合い、「大丈夫」の裏にある利用者さんの気持ちをどう汲み取るかを一緒に考えました。
彼らの真剣なまなざしを見て、「文化の違いは壁ではなく、学びのきっかけになるんだ」と気づかされました。
心に残るエピソード
今でも忘れられないのは、フィリピン出身のスタッフと利用者さんとのやり取りです。彼女は来日して間もない頃、日本語がたどたどしく、なかなか思うように気持ちを伝えられませんでした。けれども、毎日笑顔で「おはようございます」と声をかけ続けていたのです。
ある日、一人の利用者さんがぽつりと「あなたの笑顔を見ると元気が出る」と言いました。その瞬間、彼女は涙を流し、「日本で介護の仕事を選んでよかった」と話してくれました。私も胸が熱くなり、「介護は国籍を超えて、人と人がつながる仕事なんだ」と改めて実感しました。
雰囲気を変える力
外国人スタッフが入ってから、施設の雰囲気は確実に変わりました。明るい性格やユーモア、そして異なる価値観が場に新しい風を吹き込んでくれるのです。利用者さんの中には「外国の人と話せるのが楽しい」と目を輝かせる方もいて、まるで小さな国際交流の場のようになっています。
実際に、外国人スタッフが加わってから離職率が下がったという話も聞きます。私自身も、彼らと一緒に働くことで、自分の介護観を見直し、より柔軟に利用者と向き合えるようになりました。
広がる未来
2025年4月からは制度改正によって、施設系だけでなく訪問介護の分野でも外国人スタッフが働けるようになりました。この変化は、地方や小規模の事業所にとっても大きな助けになるはずです。
政府は「特定技能」全体で今後5年間に最大82万人の外国人を受け入れる方針を掲げています。その中でも介護分野は特に期待されており、今後ますます多くの仲間が現場にやってくるでしょう。
私は、その未来を楽しみにしています。なぜなら、彼らと共に働くことで、介護がもっと豊かで、もっと人間らしいものになると信じているからです。
ハッピーエンドの瞬間
ある日の夕方、施設の食堂でのこと。フィリピン人スタッフがギターを持って現れ、ベトナム人スタッフが日本語で一緒に歌い始めました。最初は驚いていた利用者さんたちも、次第に手拍子をし、笑顔で合唱に加わっていきます。日本人スタッフも輪に入り、世代も国籍も関係なく、場がひとつにまとまっていく。
その光景を見ながら、私は心の中でこう思いました。
「文化の違いは壁なんかじゃない。むしろ介護の現場を彩る大切な色なんだ」と。
そして、その温かい時間こそが、私たちが目指す介護の未来であり、ハッピーエンドなのだと信じています。