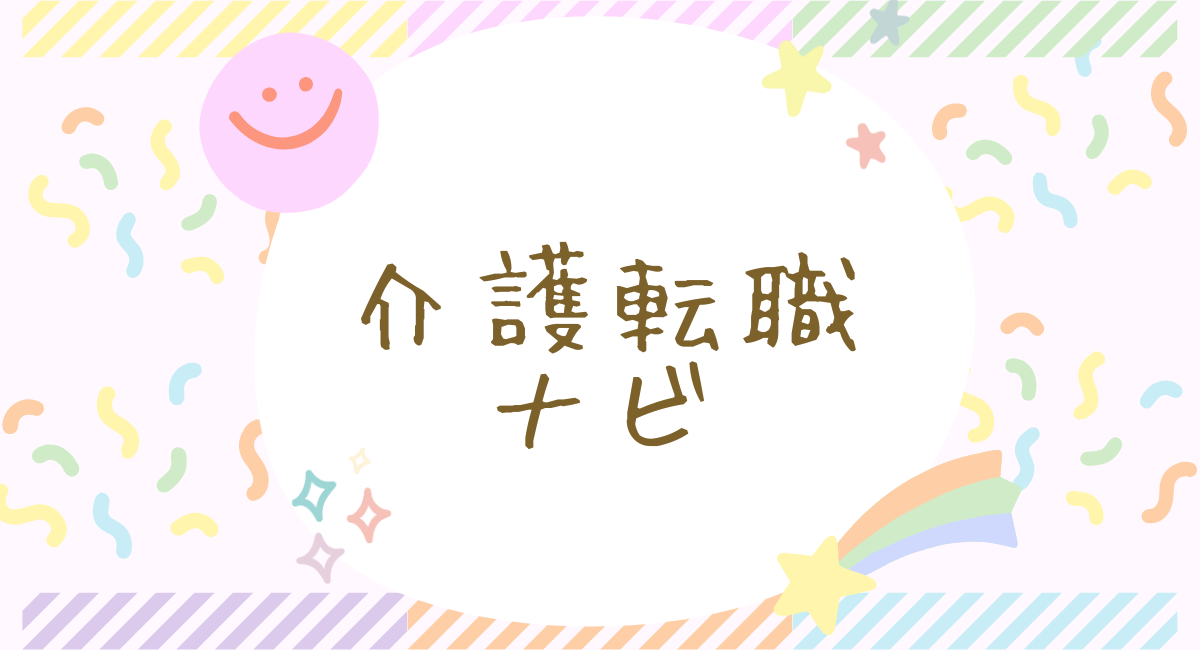■高校時代(18歳)
高校3年生の進路相談 「将来どうするんだ?」と担任の先生に聞かれた。正直、いままでは漠然としたイメージしかなかったけれど、家族の影響もあって、福祉の仕事に興味を持つようになった。祖父が介護が必要になったとき、訪問介護の人がすごくあたたかい対応をしてくれたのを覚えている。あんな風に誰かの力になれる仕事がしたいと思った。先生は「福祉系の大学に進むのもいいんじゃないか?」と背中を押してくれた。両親も反対しない。むしろ喜んでくれているみたいだ。ちょっと不安だけど、やってみようと思う。
受験勉強スタート 福祉系大学は受験科目が少し特殊かもしれない。英語・国語が中心で、小論文があるところも多い。日頃から新聞や福祉に関するニュースをチェックしておこう。将来のことを思うと勉強にもやる気が出てくる。意外と自分って、やればできるタイプかもしれない…なんて思ったり。
合格通知到着 第一志望の福祉系大学から合格通知が届いた!両親に報告したら、母親が泣きそうなくらい喜んでくれた。やっぱり、家族の期待に応えられるのはうれしい。これからがスタートだ。大学に行ったら本格的に介護の勉強が始まるんだな。ワクワクするけど、どんなことを学ぶのかドキドキも大きい。
■大学1年(18~19歳)
4月:入学式 桜の木の下で、大学の入学式。初めて出会うクラスメイトも多くて、ちょっと緊張。福祉系の学部だからか、男女比はほぼ半々くらい。みんな優しそうだし、やる気に満ちているのが伝わってくる。これから4年間、一緒に学べる仲間になるんだな。
5月:初めての専門科目 介護福祉士の国家試験対策に関連する講義が始まった。まだ1年目は基礎科目が中心だけど、身体構造や福祉理論など、今までとは違う専門的な勉強にワクワクする。でも専門用語が多くて覚えるのが大変だ。授業中は必死にノートを取り、終わった後は友人たちと復習。高校のときより勉強量が増えた感じがするが、苦にはならない。不思議だ。
7月:サークル活動 大学ではサークルにも入った。軽音サークルに興味を持って、思い切って見学したら、そのまま加入。週末にスタジオ借りて演奏練習するのが息抜きになっている。介護とは直接関係ないけど、大学生活の思い出づくりには大切かも。
8月15日:夏休みのボランティア 大学の紹介で、地元の高齢者施設にボランティアへ行く機会をもらった。食事介助の手伝いや、レクリエーションの補助をしただけだけど、利用者の方々がとても喜んでくれて、心があったかくなった。やっぱり現場に出ると、教科書とは違う発見がある。会話も大切なんだなと実感。うまく話せなかったけど、「また来てね」って言われてうれしかった。
■大学2年(19~20歳)
4月:学内実習の準備 2年生になると、実習に向けた事前学習が本格化してきた。バイタルサインの測り方や、食事介助の仕方など、実践的な技術を練習する。人形を使って練習するだけでも戸惑うのに、実際の利用者さん相手にうまくできるか不安。先生が「まずは相手の人間性を大切に」と言っていたのが印象に残る。機械的にやるんじゃなく、気持ちに寄り添うことが大切なんだって。でも人間性ってすぐにはわからないし、なかなか難しいな。。
6月:初めての実習 学内実習を経て、短期間だけど施設での実習がスタート。最初は緊張して挨拶も上手くできないくらいだったが、スタッフの先輩たちは優しく教えてくれた。利用者の方に「お兄ちゃん、がんばってね」と声をかけられ、ちょっと照れた。おむつ交換や身体介助も実際にやらせてもらった。想像以上に体力を使うし、相手への配慮が必要。自分にできるかなと不安になったけど、ここでくじけちゃいけない。
8月:夏休みの帰省 実習が終わって、一旦実家に帰省。祖父母に会うと、やっぱり高齢者との接し方がちょっと変わった気がする。自然と「大丈夫?」と声をかけたり、手を添えたりするのが習慣に。基礎知識って重要。知ってると知らないとでは大きな違いだ。
祖母からは「優しくなったね」と言われて嬉しい。介護の世界に足を踏み入れたんだと実感。
■大学3年(20~21歳)
4月:専門分野の授業が増える 3年生になると、本格的に介護福祉士の国家試験対策の授業や実習が増えてきた。コミュニケーション論やリハビリテーション概論、社会福祉制度論など、暗記だけじゃなく理解が必要な範囲が広い。バイトとサークルもあるけど、今は優先順位をつけて勉強に力を入れる時期かも。夜は図書館にこもることが多くなった。
6月:グループ研究 福祉用具についてのグループ研究が始まった。車いすやベッド、手すりなど、どんな特徴があるのか調べ、利用者に合った提案をするのが難しい。でもこういう学びが、将来実際に役に立つはず。グループメンバーは僕を含めて5人で、連日夜まで集まって準備をした。大変だけど、仲間と一緒に考える時間はそれなりに楽しい。
9月:長期実習スタート 夏休み明けから長期実習へ。今度は前回よりも期間が長い。日誌を書き、担当の利用者さんを持ち、介護計画の作成にも参加。施設の職員さんは忙しそうだが、自分の相談にも乗ってくれるし、実習指導者の方も親身にアドバイスしてくれる。夜勤体験もさせてもらって、昼間とは違う利用者さんの様子にも驚いた。夜中にトイレに起きる方への対応、深夜に見守りをする責任感。身体的にも精神的にもハードだけど、現場を知る大切さを痛感した。
■大学4年(21~22歳)
4月:就職活動開始 いよいよ就職活動が本格化。クラスメイトは病院や施設、地域包括支援センターなど、それぞれ志望が違う。僕はやっぱり特別養護老人ホームか介護老人保健施設など、入所系の施設で働きたいと思っている。現場で利用者さんに寄り添いたいのと、将来的に施設長を目指したいという夢もあるからだ。大学で学んだことを活かせる職場をしっかり探さなくちゃ。
6月:内定ゲット 大学の紹介やOB訪問などを通じて、いくつかの介護施設を見学し、面接も受けた。第一志望だった社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームから内定をもらえた!家から少し遠いけれど、施設見学のときの雰囲気がすごく良くて、職員の方々が明るかったのが決め手。来春からここで働くんだと思うと、ドキドキとやる気が混じり合った感覚になる。
10月:国家試験対策の追い込み 介護福祉士の国家試験に向け、大学では模擬試験や対策講座が連日行われている。範囲が広くて大変だけど、同期と一緒に励ましあいながら勉強するのは心強い。先生も真剣に教えてくれるし、「現場に出てから本番だよ」と言われると、ますます気合いが入る。
3月:卒業式 ついに大学卒業。国家試験の結果は合格!
これで晴れて介護福祉士の資格を得た。4年間はあっという間だったけど、いろいろなことを学んだし、自分なりに成長できたと思う。明日からは社会人。旅立ちの春、いろんな期待を胸に抱いて、一歩を踏み出す。ほんとは不安いっぱいなんだけど…。
■社会人1~2年目(22~24歳)
4月:社会人初日 特別養護老人ホームに入職。入社式で同時に入ったメンバーは5人。みんな介護福祉士の資格を持っていて、同年代だから心強い。辞令を受け取って配属されたのは「第2フロア」。早速先輩について業務の流れを学ぶ。挨拶回りも兼ねて、利用者さんに顔を覚えてもらう。緊張で汗が止まらない。
5月:初めての夜勤 入職して1か月。仕事には少し慣れたけど、覚えることは山ほどある。早番、遅番、夜勤シフトがあるのが慌ただしい。今日はついに一人で夜勤を担当する日。といっても先輩が一緒なので安心だが、真夜中のコールは想像以上に多い。夜間は利用者さんも不安定になりやすいし、転倒などのリスクもある。頭の中は常に「何かあったらどうしよう」という緊張感でいっぱい。でも終わってみると、無事に朝を迎えられたという達成感があった。
10月:先輩からのアドバイス 半年が過ぎ、ようやく業務の流れには慣れてきた。でもバタバタしていると利用者さんへの声かけが雑になってしまうことがある。先輩に「忙しいときほど、相手の目を見て挨拶する。それができるだけで違う」と言われ、ハッとした。
自分は目の前の業務に追われがちだったかもしれない。改めて“介護”は人と人との関わりで成り立つものだと再認識した。コミュケーションが取れてこその仕事だよね。
2年目・4月:後輩ができた 今年新しく入ってきた職員の指導担当を任された。まだ自分も2年目なのに、後輩に教えるって早すぎるんじゃ…と思ったけど、先輩たちが「君ならできる」と言ってくれたので引き受けた。教えることで自分の理解不足や業務の甘さを痛感する。介護技術の再確認にもなるし、後輩が「わからない」と言ってきたとき、どう説明すれば納得してもらえるか頭を使う。人に教えるって今まで以上に自分に知識がないと自信もって教えてあげられない。もっと勉強しなくては。
色々あるけど、なんだかんだで充実している。
■社会人3~4年目(24~26歳)
3年目・5月:リーダー候補の話 上司から「そろそろリーダーを意識して勉強してほしい」と言われた。え、もう?という感覚でしかないのだけれど‥。
リーダー職になると、業務管理やシフト調整、研修の実施なども任されるらしい。一職員として利用者さんに向き合うのと並行して、組織運営のことも考えなきゃいけない。まだ自分には荷が重い気しかしないけど、上司の期待に応えたい気持ちもちょっとある。
3年目・8月初めての大失敗 夜勤明けでヘトヘトだったこともあり、うっかり書類の提出を忘れてしまった。翌日に上司から「提出期限が過ぎている」と注意を受け、平謝り。しかも業務報告も漏れていたらしい。忙しさにかまけて、管理能力が低い自分を痛感した。これを機に、スケジュール管理アプリを使うようにしたし、報・連・相を意識して徹底しようと決意した。
4年目・2月:結婚を考え始める プライベートの話。実は大学時代から付き合っていた彼女と、そろそろ結婚を意識している。仕事は不規則だし、給料もまだ高くはない。彼女はそれでも「あなたの仕事は素晴らしい」と応援してくれる。一緒に生きていくなら早めに決めたいな、と思うようになった。職場の先輩には既婚者も多いけど、家庭との両立は大変そう。でも家に帰って誰かが待っていてくれるのは心強いかもしれない。
■社会人5~6年目(26~28歳)
5年目・4月:ユニットリーダーに就任 正式にユニットリーダーに昇格。自分の所属するフロアの一部をまとめる立場になる。メンバーは5人くらいで、業務を振り分けたり、利用者の情報を共有したりと、管理業務が増えた。慣れないExcelでシフト表を作ったり、会議を取り仕切ったり。大変だが、自分がやりたかった“ステップアップ”の第一歩だと思うとやりがいもある。パソコン苦手かも。。
5年目・9月:結婚式 私生活では、ついに彼女と結婚!式には職場の同僚や利用者さんからのお祝いのメッセージもいただいた。コロナ禍で規模は小さめだったけど、家族や友人に囲まれた穏やかな式になった。職場の仲間から「夫婦二人三脚でがんばれよ」と励まされ、もっと頑張ろうと思えた。
6年目・6月:ケアマネジャー受験を決意 介護福祉士としての実務経験が5年以上経ったので、そろそろ介護支援専門員(ケアマネ)の資格にチャレンジしようと思う。リーダー業務もあって時間のやりくりが大変だけど、施設長を目指すならケアマネの視点は欠かせないはず。妻も「頑張りなよ」と背中を押してくれる。
6年目・10月:ケアマネ試験 猛勉強の成果を出すときがきた。試験は難易度が高いと聞いていたが、本当に幅広い知識が問われる。特に介護保険制度や社会福祉の法律関係がややこしくて苦戦。でも、勉強していくうちに「制度」を理解することで、利用者の暮らしをどう支えられるのかが見えてくる。あとは結果を待つだけ。
■社会人7~9年目(28~30歳)
7年目・1月:ケアマネ合格通知 ドキドキしながら封を開けると、「合格」の二文字が!やった!これで介護支援専門員としての登録ができる。上司や同僚からも「おめでとう。これからさらに活躍してもらうよ!」と言われて身が引き締まる。
7年目・4月:ケアマネとしての業務スタート 施設内でのケアマネ業務を一部担当することに。ユニットリーダーとケアマネ業務を兼任する形だ。利用者一人ひとりのケアプランを作成し、家族や医療機関との連携を図る。書類仕事も増えたし、アセスメントの時間も必要。正直、現場での介護とマネジメントの両立はしんどい。でも、利用者さんや家族の状況を深く知り、サポート内容を考えるプロセスはやりがいがある。
8年目・10月:管理職候補の研修へ 法人が開催する管理職向けの研修プログラムに参加することになった。リーダーやケアマネとして実績を重ねてきたからか、声をかけてもらえたらしい。研修では、経営や人事管理、リスクマネジメントなど、普段あまり意識していなかったテーマを学ぶ。会社組織として運営する視点を持たないと、施設長は務まらないんだなと実感。
9年目・3月:主任ポジションに就任 ユニットリーダー兼ケアマネを続けながら、今度は「主任」という肩書がついた。複数のユニットを跨いで調整する業務も任される。職員の面談や指導、書類の最終チェックなど、さらに責任が重くなった。妻は「身体壊さないでね」と心配してくれる。自分でもスケジュール管理を見直しつつ、同僚に協力を仰ぐようにしている。
■社会人10~12年目(30~32歳)
10年目・5月:30歳の節目 仕事に追われていたら、いつの間にか30歳。今では部下も増え、後輩たちを見守る立場になっている。施設長を目指すとはいえ、まだまだ経験不足な気がする。先輩の施設長は「人を育てることが大事だよ。自分一人で抱え込まない」とアドバイスをくれた。まわりを活かす組織づくりが課題なんだろう。
10年目・11月:子供が生まれる 私生活でも大きな出来事が。第一子となる長男が誕生!立ち会い出産で妻が頑張っている姿を見て、命の重みをひしひしと感じた。子育てと仕事の両立は思った以上に大変。夜泣きで寝不足の日もあるが、その分家族の存在がモチベーションになる。施設の職員仲間も「いいパパになってね」と応援してくれるのがありがたい。
11年目・7月:管理者研修への参加 法人が自治体や関連団体と連携して行う「管理者研修」に参加。施設長や管理職を目指す者が集まるので、刺激を受ける。そこで会った同年代の管理者は、「マネジメントは難しいけど、やりがいがある」と口をそろえて言う。お互いの苦労話を共有しつつ、学びあえる仲間ができたのは大きい。
12年目・2月:副施設長への打診 上司から呼び出され、「来年度から副施設長をやってみないか?」と打診された。正直、主任になってまだ数年。施設の運営全体を把握するには早い気もするが、ここで断るわけにはいかない。夢だった“施設長への道”が一歩近づいていると考えれば、やるしかない。上司も「大丈夫、困ったら相談しなさい」と言ってくれたので心強い。
■社会人13~15年目(32~34歳)
13年目・4月:副施設長に就任 正式に副施設長として着任。現場を指揮する立場から、今度は経営や人事、地域との連携など、さらに幅広い業務を担当することに。会議も増え、外部団体との調整や行政対応も発生する。書類仕事や会議準備で、毎日が嵐のように過ぎる。だけど、やりたかった道だからこそ、やる気も満ちている。
14年目・10月:先輩施設長との衝突 運営方針をめぐり、施設長である先輩と意見が対立。利用者のためにもっと手厚い介護体制を組みたいが、予算的にも職員数的にも難しい。現実的な線を模索するのが管理職の仕事なんだと、改めて学んだ。感情的になると周囲が混乱するだけ。冷静な判断と根回し、そして説得力が必要だと痛感する。自分の思いだけではみんなは回らないというか、何が必要であるかを学んだ気がする。
15年目・3月:法人の大規模改修計画 法人が運営する施設の増築と改修が決定。副施設長として、工事担当者や行政と打ち合わせを行う日々。こんな大きなプロジェクトに関われるなんて予想していなかった。施設の設計にまで意見を出せるのはやりがいがあるが、同時に責任が重い。でも「利用者が快適に暮らせる空間を作る」という根本をぶらさないようにしたい。
■社会人16~18年目(34~36歳)
16年目・5月:施設長が退任予定 これまで施設を引っ張ってきた施設長が体調面の都合で退任するという話が出てきた。上司からは「君が後任候補に挙がっている。やる気はあるか?」と聞かれる。自分はまだ副施設長として2年くらいしか経っていない。でも法人は実績や評価を総合的に見てくれているようだ。正直、覚悟はしていたけど、本当に自分がなっていいのか不安にもなる。
17年目・1月:引き継ぎ準備 施設長から業務引き継ぎを受け始める。法人全体の財務状況や職員の人事計画、地域との連携事業など、把握すべきことが山ほど。覚悟はしていたが、想像以上に守備範囲が広い。施設長は「焦らなくていい、一つずつ覚えていけばいいから」と言ってくれるが、不安と期待が入り混じる日々。
18年目・3月:送別会 長年お世話になった施設長が退任。送別会では多くの職員や利用者家族が「本当にお疲れ様でした」と感謝を伝えていた。施設長は去り際に「あとは頼んだよ」と僕の肩をぽんと叩いた。なんだか胸が熱くなって、涙が出そうになる。ここまで導いてくれた恩は絶対に忘れない。
■社会人19年目(36~37歳)
4月:施設長に就任 ついに自分が施設長としての辞令を受ける日がきた。正式に「施設長」と呼ばれると、身が引き締まる思いだ。この施設には100名以上の利用者がおり、職員も50名以上。僕が大学を出てから数えて、もう15年以上この世界で働いているが、まだまだ学ぶことは多い。
4月:初めての施設長会議 地域の福祉施設長が集まる定例会議に出席。ベテランの施設長ばかりで、皆さん経験豊富。僕はまだ新人施設長なので緊張する。でも、介護報酬や地域包括ケアシステムの動向など、経営面の情報を交換できる貴重な場だと感じる。先輩施設長たちに可愛がってもらえるよう、謙虚に学ぼう。
6月:経営面での悩み 新年度の予算編成を進める中で、収益と支出のバランス、職員給与の見直しなどに頭を抱える。介護報酬の改定があり、収益が下がる可能性も出てきた。ここをどう乗り越えるかが腕の見せ所。現場にも理解を求めつつ、なるべく負担をかけない方法を模索する。施設長室で一人残って検討することも多いけど、やはり周囲を巻き込みながら知恵を出すことが大事だ。
8月:ご利用者からの嬉しい言葉 ある利用者のご家族が面談で「ここに預けてよかった。職員さんが皆さん優しくて、父はとても幸せそう」と涙を浮かべながら言ってくれた。運営面では悩みが尽きないが、こういう言葉を聞くと「やってよかった」と思える。スタッフの頑張りが評価されている証拠でもあるから、しっかりと感謝を伝えたい。
■社会人20年目(37~38歳)
4月:施設長として1年経過 あっという間に1年が過ぎた。試行錯誤の連続だったが、職員たちが支えてくれたおかげで大きなトラブルもなく施設を運営できている。法人本部からは「今後はさらに地域との連携事業を進めてほしい」と言われている。地元の中学校での介護体験授業を企画したり、地域の医療機関との連携強化を図ったり。やるべきことは山積みだけど、やりがいも大きい。
6月:子供の将来 プライベートでは、長男が小学校に入学。子供の成長は早い。仕事で忙しくても、家族との時間を大切にしなきゃと強く思う。妻も僕の仕事を理解してくれているから、本当にありがたい。子供からは「お父さんはおじいちゃんおばあちゃんを助ける仕事なんだよね?」と聞かれて、誇らしいような気恥ずかしいような、不思議な気分。
10月:法人内での評価 定期的な法人内の評価面談があり、上司にあたる理事長と面談。「新しい取り組みに意欲的で、若手職員をうまく引っ張っている」と評価をもらえた。もちろん課題も指摘されるが、施設長1年目としては上出来とのこと。職員の意見をもっと汲み上げる仕組みや、離職率の低減にも力を入れるよう言われる。まだまだ道は長い。
12月:大晦日の感慨 今年は施設長としての初めての年末年始を迎える。年越しイベントやおせちの準備、職員のシフト調整など慌ただしいが、利用者さんにとっては大切な行事だ。心を込めて準備をしたい。ふと、自分が高校生の頃、祖父の介護を見て感じたあの気持ちが蘇る。あの時はぼんやりと「誰かの役に立ちたい」と思っただけだった。でも、今こうして多くの人を支える立場にいることを考えると、人生ってわからないものだ。
■エピローグ
高校を卒業してから約20年。福祉系大学で学び、介護福祉士として現場で経験を積み、ケアマネ資格を取って、主任・副施設長を経て、施設長となった。振り返ると、失敗や挫折、悩みも多かったが、そのたびに周囲の人が支えてくれた。こんなに人に接する仕事ってやはり充実感があると思う。別れもあるけど、みんなの支えあっての今の自分だ。
毎日が学びで、まだまだ理想に到達したわけじゃない。でも、「誰かの人生に寄り添える仕事がしたい」という最初の想いは、今でも胸に生き続けている。これからも利用者さんや家族、そして職員の笑顔を守るために、地域に根ざした施設運営を目指していこう。そんな決意とともに、今日も施設の扉を開ける。