介護職員の現場の悩みと疑問に答えます|よくある質問40選
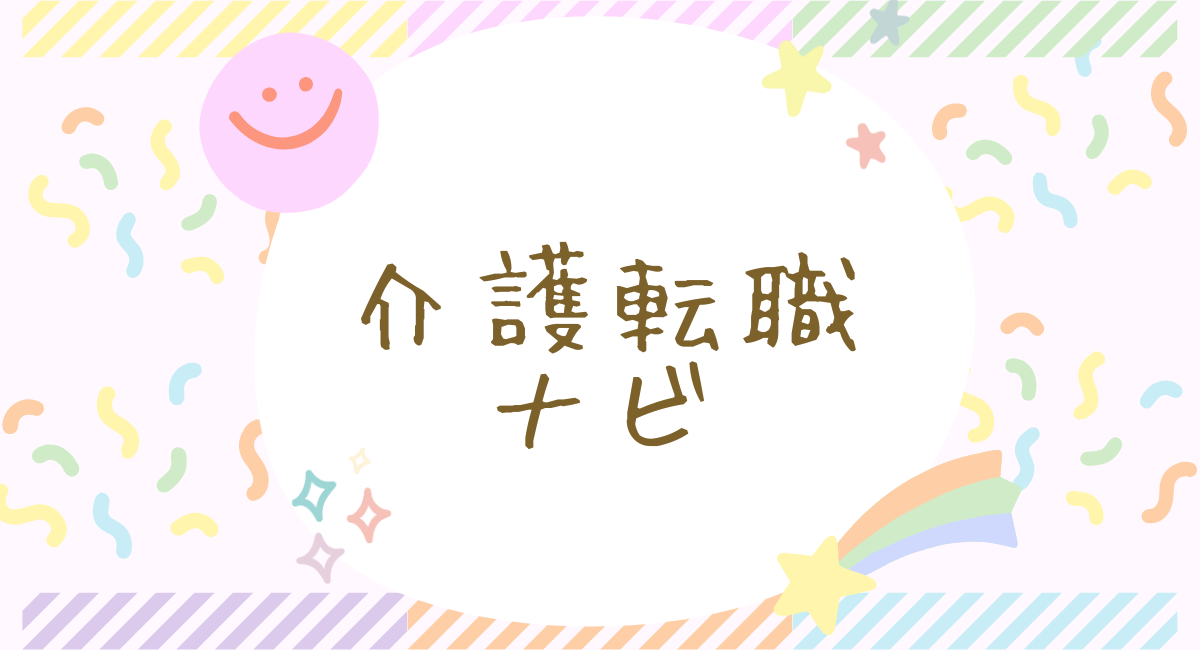
✅介護職員のよくある悩み
Q1. 介護職の給与はなぜ低いのですか?今後改善される見込みは?
A. 介護職の給与が他業種に比べて低いと感じる方は多く、その背景には「介護報酬制度」があります。介護保険制度の枠内で事業所が得る収入が決まっており、人件費に大きく割けない仕組みとなっています。
ただし、国は「処遇改善加算」や「ベースアップ加算」などを設けており、キャリアアップや資格取得によって給与が上がる環境も整いつつあります。また、経営努力により高待遇を実現している法人もあるため、職場選びが重要です。各社の求人条件をよく確認して実際の給与と納得できる職場環境であることを重要視する姿勢が大切です。
Q2. 賞与が少なくて不満です。他の職員はどうしていますか?
A. 介護業界では、賞与(ボーナス)の支給は法人の財政状況に左右されやすく、支給されない場合もあります。そのため、生活設計に不安を抱える職員も少なくありません。
中には副業を許可された施設でダブルワークをしている方や、賞与が安定して支給される法人へ転職するケースもあります。年収ベースでの待遇や福利厚生も含めて、自身の価値観に合った職場を選ぶことが大切です。税金の影響も踏まえてダブルワークのボリュームを検討してみることをお勧めします。
Q3. サービス残業が常態化しています。断っても大丈夫?
A. サービス残業は労働基準法違反であり、本来は断って当然のものです。ですが現場では「人手が足りないから」「みんなやっているから」と断りにくい空気があるのも現実です。
まずは、自身の業務時間を記録し、上司に正式に相談することが第一歩です。改善されない場合は、労働組合や労働基準監督署に相談することも検討しましょう。自分の健康と権利を守ることが、長く働くためには不可欠です。
Q4. 夜勤が体にこたえます。皆さんどうやって乗り越えていますか?
A. 夜勤は心身に大きな負担をかけます。生活リズムが崩れやすく、疲労がたまりやすいため、対策が必要です。多くの方は、夜勤明けの休息をしっかり取り、日中でも仮眠を入れるように工夫しています。
また、夜勤の回数を調整してもらう交渉をしたり、体調が悪いときは正直に申し出ることも大切です。「夜勤専門の職員」を採用している事業所もあるので、自分に合った働き方を探すのも一つの手です。
Q5. 利用者の名前がなかなか覚えられません。コツはありますか?
A. 名前を覚えるには、「顔と名前をセットで覚える」「エピソードを関連付ける」といった方法が効果的です。たとえば「Aさんはお花が好きな方」といった具合に、個性と名前を結びつけると記憶に残りやすくなります。
また、利用者名簿を毎朝確認したり、名前を声に出して呼ぶ習慣を持つこともおすすめです。焦らず、少しずつ親しみながら覚えていきましょう。
Q6. 認知症の利用者が「家に帰りたい」と言ったらどう対応すべき?
A. 認知症の方の「家に帰りたい」という言葉は、不安や混乱の表れであることが多いです。まずは否定せず、「どんなところに帰りたいですか?」など、話を受け止めて安心させることが大切です。
可能であれば、本人が落ち着く環境(写真、音楽、においなど)を用意して、居場所の安心感を取り戻す工夫をするとよいでしょう。無理に説得せず、気持ちに寄り添う姿勢が求められます。
Q7. 上司が感情的になりやすくて困っています。どうすれば?
A. 感情的な上司との関係に悩む人は少なくありません。まずは、冷静に対応する姿勢を保ち、必要以上に反応しないことが大切です。タイミングを見て落ち着いた時に、伝えるべきことを話すのが有効です。
職場に信頼できる第三者がいるなら、相談してクッション役になってもらうのもよいでしょう。改善が難しい場合は、他部署への異動希望や、外部相談窓口を利用する方法もあります。
Q8. 利用者から暴言を受けました。どう対処すれば?
A. 利用者の暴言に心を痛める職員は多いですが、まず大前提として「暴言を許容する必要はない」ということを知ってください。認知症や精神疾患の影響による場合でも、ケアにあたる側の心の健康も重要です。
対応としては、冷静に距離を取り、安全を確保したうえで、記録し、チームで共有することが大切です。心理的な負担が続く場合は、早めに上司や外部相談窓口へ相談してください。
Q9. レクリエーションの企画が苦手です。どうすれば良い?
A. レクリエーションが苦手な方は多いですが、無理に盛り上げ役になる必要はありません。大切なのは「利用者が楽しんでくれること」です。簡単な体操、昔話、歌、塗り絵など、小さな工夫で十分です。
YouTubeや福祉施設の資料などから事例を調べ、型を真似ることから始めましょう。職員同士でアイデアを共有するのも、負担軽減になります。
Q10. 体力的に仕事がきつくなってきました。辞めるべきでしょうか?
A. 体力の衰えを感じた時に「辞めるしかない」と思いがちですが、まずは働き方の見直しをおすすめします。夜勤を外して日勤専従にする、勤務日数を減らす、身体介助の少ない業務にシフトするなど、方法はあります。
また、デイサービスや相談業務など、体力負担が少ない職種に異動・転職することも一つの選択肢です。介護職の経験は、さまざまな形で活かすことができます。
✅介護職員のリアルな悩みと対応
Q11. 同僚との関係がギクシャクしています。どうすれば良い?
A. 同僚との関係は日々の仕事に大きく影響しますよね。特に介護現場では、連携が取れていないと業務が円滑に回らなくなってしまいます。まずは「報告・連絡・相談」を意識して、最低限のコミュニケーションから始めてみましょう。
相手の得意なことを認めたり、簡単な「ありがとう」の一言を伝えることで、関係が徐々に改善されることもあります。それでも難しい場合は、上司に相談して配置の見直しを検討してもよいでしょう。
Q12. 医師や看護師とのやり取りが苦手です。どう乗り越える?
A. 医療職との連携は、緊張感や立場の違いからストレスを感じやすいものです。まずは「専門職としての対等な立場」であることを自覚し、報告や連絡をシンプルに的確に伝えることを意識しましょう。
また、医師や看護師の言葉にわからないことがあっても、素直に聞き返すことで信頼関係が築けるケースもあります。共通の目的は「利用者のため」であることを忘れず、敵対ではなく連携を目指すことが大切です。
Q13. 入浴介助が苦手です。安全にこなすには?
A. 入浴介助は滑りやすく、事故のリスクもあるため、苦手意識を持つ方も多いです。まずは基本動作(立位保持、移乗動作)を確認し、2人体制が必要な場面では無理せず応援を依頼しましょう。
また、事前の声かけ・環境整備(床の滑り止め、温度確認など)も重要です。不安な場合は、ベテラン職員の動きを観察したり、福祉用具を積極的に活用するのも安全性向上につながります。
Q14. 排泄介助に抵抗があります。どう受け止めれば?
A. 排泄介助に対する心理的なハードルは誰しも感じるものです。まずは「その人の尊厳を守る行為」であることを意識して向き合いましょう。利用者の立場になって考えると、「見られることの恥ずかしさ」や「不安」も理解できるはずです。
声かけや表情、配慮のある態度が信頼関係の構築につながります。経験を重ねるうちに、自然と抵抗感は薄れていきます。
Q15. 利用者の家族から無理な要求をされました。どう対応する?
A. 家族からの要望はときに過剰で、職員を困らせることもあります。まずは「相手の不安の背景」を理解する姿勢で話を聞きましょう。それでも理不尽な要求が続く場合は、記録を取り、上司やサービス提供責任者に相談することが大切です。
職員が一人で背負い込まず、組織として対応する姿勢を示すことが、トラブルの拡大防止になります。
Q16. 認知症の方が暴れてしまいます。どうすれば?
A. 急に大声を出したり、暴力的な行動に出る認知症の利用者に対しては、まず「驚かせない・刺激しない・急がせない」が基本です。本人は恐怖や混乱からそのような行動をとっている可能性があります。
落ち着いた声で声かけし、安全を確保したうえで、しばらく距離を置くのも有効です。日頃の様子を観察して、「何がきっかけで不穏になるか」を記録しておくと、今後の予防につながります。
Q17. ミスをしてしまいました。どう報告すれば?
A. ミスは誰にでもあります。重要なのは、すぐに報告・連絡・相談を行い、隠さないことです。報告の際は「事実」「原因」「今後の対策」を簡潔に伝えることを意識しましょう。
また、同じミスを繰り返さないよう、周囲と一緒に対策を練ることも大切です。「ミス=評価が下がる」ではなく、「改善に取り組む姿勢」が評価される風土づくりも求められます。
Q18. クレーム対応が苦手です。コツはありますか?
A. クレームは誰でも落ち込むものですが、感情的にならず「傾聴の姿勢」を持つことが第一です。まずは相手の話をさえぎらずに聞き、「ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありません」と共感を示すだけで相手のトーンが落ち着くことがあります。
その上で、必要な情報を整理し、上司や関係者と共有して組織的に対応しましょう。一人で抱え込まないことがクレーム対応の鉄則です。
Q19. 有給休暇がとりにくいです。どう交渉すれば?
A. 有給休暇は労働者の権利ですが、介護職では「人手不足だから」「迷惑をかけたくない」と遠慮しがちです。まずは「計画的に事前申請」し、業務調整の相談を早めにすることがスムーズな取得のコツです。
「取得理由を細かく言わない」「休むことに罪悪感を持たない」意識も大切です。有給取得率は職場改善の指標でもあるため、チーム全体で休みやすい雰囲気づくりを心がけましょう。
Q20. モチベーションが続きません。どう維持すれば?
A. 介護の仕事は感謝される場面も多い反面、心身の疲労でモチベーションを保ちにくい時期もあります。そんなときは、自分の働く意味や、利用者の「ありがとう」を思い出すことで立ち直る方も多いです。
また、業務だけでなく、「学び」や「趣味」に目を向けることも、良いリフレッシュになります。定期的に「なぜ介護の仕事を選んだのか」を振り返ることも、原点に立ち返るきっかけになります。
✅キャリア・家庭との両立・ストレスの向き合い方
Q21. 介護の仕事に将来性はありますか?
A. はい、介護業界は今後ますます需要が高まる分野です。高齢化が進む日本において、介護職は「必要とされ続ける仕事」の代表格ともいえます。
また、国の施策でも介護職の地位向上や待遇改善が進められており、今後はICT導入や専門性の高い分野(認知症ケア、看取りなど)でのスキルが求められるようになります。スキル次第でキャリアアップや異業種連携の道も開けます。
Q22. スキルアップしたいけど、何から始めればいい?
A. まずは「介護福祉士」の国家資格を目指すことをおすすめします。初任者研修→実務者研修→介護福祉士という流れが一般的です。
その後も、「認知症介護実践者研修」「サービス提供責任者研修」「ケアマネジャー」など、興味や職場環境に合わせたスキルを選ぶと良いでしょう。法人によっては研修費の補助制度もあるため、確認してみましょう。
Q23. キャリアチェンジを考えています。どんな選択肢がありますか?
A. 介護職の経験は、さまざまな分野で活かせます。たとえば、「相談員」「ケアマネジャー」「福祉用具専門相談員」「講師」などは、現場経験を活かせる職種です。
また、事務職や福祉系NPOへの転職、独立開業(フリーランス介護士や訪問介護事業)も選択肢に入ります。自分の得意分野や価値観を整理し、専門職としての視野を広げていきましょう。
Q24. 育児と仕事の両立が難しいです。みんなどうしてますか?
A. 子育て中の介護職員は少なくありません。まずは「時短勤務」「日勤専従」「扶養内パート」など、自身に合った働き方を探すことが大切です。
保育園や学童の送迎に対応しやすい職場を選ぶ、家族やパートナーと家事を分担する、など生活全体で調整が求められます。事業所によっては、子育て支援制度(子連れ出勤など)を設けている所もあります。
Q25. 家族の介護と仕事が重なってきました。どうすれば?
A. 「ダブルケア」は身体的にも精神的にも負担が大きく、ひとりで抱え込むのは危険です。まずは勤務先に事情を説明し、シフトや業務内容の調整を相談しましょう。
同時に、自治体の「介護者支援サービス」や「ケアマネジャー」にも相談することで、在宅介護の負担を減らす支援策が見つかるかもしれません。公的制度をフル活用する意識が大切です。
Q26. 感情のコントロールができません。利用者にイライラしてしまいます。
A. どんなに経験があっても、感情が揺れるのは当然です。疲れていたり、思うようにケアが進まないときは、自己嫌悪に陥ることもあるでしょう。
大切なのは、「感情を否定しない」ことです。「今、自分は疲れている」と自覚し、誰かに共有するだけで、気持ちが整理されることもあります。職場で定期的な感情リフレクションの時間を持つことも効果的です。
Q27. 利用者が亡くなったとき、気持ちの整理がつきません。
A. 利用者の死は、心に大きな影響を与えるものです。悲しみを感じるのは自然なことで、「もっとできたかもしれない」という思いも湧いてきます。
この気持ちを職員同士で共有したり、事業所で「看取りの振り返り」を行う文化があると、前向きに乗り越えやすくなります。必要ならば外部のカウンセリングを利用するのもひとつです。
Q28. ストレスで体調を崩しました。復帰が不安です。
A. ストレスによる体調不良は、身体からの「限界サイン」です。まずは無理に復帰せず、医師と相談のうえで休養をしっかり取ることが最優先です。
復職の際には「短時間勤務」「業務の一部から再開」など、職場と段階的な調整を行いましょう。復帰後に再発を防ぐためには、相談できる仲間や支援体制を整えておくことが重要です。
Q29. 職場でいじめのような扱いを受けています。
A. 明らかな無視や陰口、排除などがあれば、それは「ハラスメント」に該当します。まずは事実を記録し、信頼できる上司や外部相談窓口(労基署や福祉人材センター)に相談してください。
介護の現場では「人間関係」が離職理由の上位に入ります。早めに動くことで、精神的なダメージを減らし、自分自身を守ることができます。
Q30. 転職を考えていますが、どこを見て選べばよいですか?
A. 転職を成功させるには、「条件」だけでなく「理念」「人間関係」「研修制度」など、職場の文化も見極めることが大切です。見学時の職員の雰囲気や、面接での対応も重要な判断材料です。
また、ハローワークや福祉系転職エージェントを利用することで、内情を聞いた上で選ぶこともできます。「自分に合った職場とは何か?」を明確にすることから始めてみてください。
✅働き続けるために知っておきたいこと
Q31. 同僚がサボっていて不公平に感じます。どうすれば?
A. 誰かが楽をしていると、自分ばかりが大変な思いをしているように感じてしまいますよね。ただ、まずは「事実ベース」で状況を捉えることが大切です。
あからさまな勤務態度の差がある場合は、感情的にならずに上司に相談しましょう。「誰が悪い」ではなく「チームとしてどう改善するか」を視点にすれば、建設的な解決につながります。
Q32. 利用者から「あなたじゃない人にして」と言われました。傷つきます。
A. そのような言葉は心に刺さりますよね。ただし、利用者の言葉には認知症や気分、タイミングの影響がある場合も多いです。個人的に否定されたと受け取らず、「今はその方の気持ちが不安定なのだ」と距離を取ってみてください。
後日には態度が一変することもあります。必要以上に引きずらず、チームで共有して対応を分散することも有効です。
Q33. 介護記録が面倒です。省略してもいいですか?
A. 記録は「自分を守る」「チームケアを支える」「事業所の信頼性を保つ」ために不可欠です。たとえば事故やクレームが発生したとき、記録が不十分だと責任を問われかねません。
とはいえ、忙しい中で時間が取れないのも事実。テンプレートや音声入力など、効率化の仕組みを導入することで、記録作業の負担は減らせます。
Q34. 介護ロボットやICTって実際使えるんですか?
A. はい、現在多くの施設で活用が進んでいます。移乗サポートロボットや見守りセンサー、電子記録システムなどは、職員の負担を大きく減らす効果があります。
最初は使いこなすのに時間がかかるかもしれませんが、長期的には「腰痛予防」や「転倒防止」などにもつながります。導入施設を選ぶことも、今後の働きやすさを左右するポイントです。
Q35. 食事介助のときに話しかけてもいいの?
A. はい、むしろ「楽しい食事」は利用者のQOL向上にもつながるため、会話は大切です。ただし、誤嚥のリスクがある方には、咀嚼や嚥下のタイミングに注意しながら行うことが必要です。
無理に話をさせず、タイミングを見て「おいしいですか?」など短い声かけを入れると、安心感につながります。利用者の状態に合わせた対応が大事です。
Q36. 働いても働いても生活が苦しいです。なぜ?
A. 介護職の給与水準は他業種と比べてまだ十分とは言えず、「手取りが少ない」という声も多いです。特に非正規雇用の場合、年収が200万円台にとどまることもあります。
処遇改善加算やベースアップ加算を反映している事業所を選ぶ、資格を取得して収入を上げる、副業や転職を検討するなど、選択肢はあります。生活を守るためにも、待遇面に積極的に目を向けましょう。
Q37. 体力の限界を感じています。どうしたら長く働けますか?
A. 年齢とともに体力的に厳しくなるのは自然なことです。まずは夜勤や重労働の回数を見直し、日勤や軽作業中心にシフトする方法があります。
また、介護予防事業や訪問介護、相談員業務など、身体的負担が比較的少ない仕事への移行も一案です。無理を続けるのではなく、自分のペースで働き続けられる環境を整えることが大切です。
Q38. 働いていて「やりがい」を見失いました。
A. 介護の仕事は「ありがとう」の言葉が支えになる一方で、繰り返しの日々や人間関係のストレスでやりがいを見失うこともあります。
そんなときは、小さな成功体験を意識して記録したり、「なぜこの仕事を選んだのか」を振り返ってみてください。学び直しや新しい職種への挑戦も、再びやりがいを見つけるきっかけになることがあります。
Q39. 新人職員の指導が難しいです。どう接すれば?
A. 新人には「やる気があるけど不安も大きい」という心理があります。最初から完璧を求めず、わかりやすく説明し、できたことを褒める姿勢を心がけましょう。
また、「見守る時間」と「フォローする時間」のバランスが大切です。育てようとしすぎず、自然に慣れてもらうことが定着の鍵になります。指導は「共に成長するプロセス」と捉えると気持ちが楽になります。
Q40. もう辞めようか迷っています。続けるべきでしょうか?
A. 辞めたいと思う気持ちには、必ず理由があります。「疲れすぎている」「人間関係が辛い」「家庭と両立できない」など、まずはその理由を整理しましょう。
辞めることで自分を守れるなら、それは前向きな選択です。ただし、「今の職場を辞める」=「介護職を辞める」ではありません。職場を変えることで、やりがいを取り戻す方もたくさんいます。
【おわりに】
介護の現場で働く皆さんが日々感じている悩みや疑問には、正解のないものもたくさんあります。
ですが、それを言葉にし、共有し、改善のために一歩を踏み出すことが、働きやすさの第一歩です。
本記事が、皆さんの悩みに少しでも寄り添い、「あ、自分だけじゃない」と感じられる機会になれば幸いです。
介護という大切な仕事を支える一人ひとりが、健康で安心して働ける環境を得られますように。